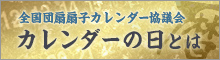団扇・扇子
扇子の出来るまで
伝統的な京扇子の製造工程を順を追って説明します。
1【胴切(どうぎり)】
竹の胴を扇子のサイズに合わせて切断します。
2【割竹(わりたけ)】
扇子のサイズに竹を割きます。
3【せん引(せんびき)】
割竹を必要な厚さまで薄く削ぎ、三枚に割きます。
4【目もみ】
要を通す穴をあけます。
5【あてつけ(扇骨成型)】
扇骨に細工を施します。

6【白干し(しらぼし)】
扇骨を干します。

7【磨き(みがき)】
扇骨に細工を施します。
8【要打ち(かなめうち)】
要を打ちます。
絹扇の場合
紙扇(かみせん)と異なり絹扇では要を打つ前に「附け」を行います。附け台の上に地紙を裏面にして乗せ糊の付いた中骨を附け台の目穴(めあな)くぎに裏向けで差し込み折地(おりじ)に手早く一本一本附けてゆきます。固定した後、あて紙を取り要を打ちます。

9【末削(すえすき)】
紙の間に入る扇骨を薄く細く削ります。

10【合わせ(あわせ)】
紙を作ります。
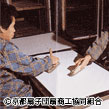
11【乾燥】
紙を乾かします。
12【裁断】
紙を裁断します。
13【箔押し(はくおし)】
紙に箔を置きます。
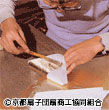
14【上絵(うわえ)】
手描きで絵を付けます。

15【木版画摺り(もくはんがずり)】
彫刻された絵柄を摺っていきます。
16【折り(おり)】
扇子の形になるように折ります。

17【中差し(なかざし)】
細竹で仲骨の差し込み口をあけます。
18【万切(まんぎり)】
地紙を折りたたみ、揃えて切ります。
19【中附け(なかつけ)】
中差し部分に骨を通します。
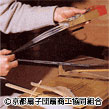
20【万力掛け(まんりきがけ)】
扇子の形を作ります。
21【親あて(おやあて)】
両端の親骨を付けます。
22【完成】
検品後、荷造りをして出荷されます。
提供:京都扇子団扇商工協同組合